前回の記事で自分の中でビールがどういう存在であったのか、またビールにハマり始めたきっかけについて綴りました。大学時代は、ビールにハマったといってもあくまで一般的なビール、そう、ピルスナーのスタイルが好きになったんです。でもそれも、多くの人が声にする「とりあえずビール!」的な存在だったんです。
では、私はいつクラフトビールに出逢ったのでしょうか。
実は、社会人になっていきなりクラフトビールに出逢ったわけではなく、食やお酒の世界を素敵だなと思えるようになったのがきっかけだったんです。
お酒は人間を幸せな気持ちにしてくれるものなんだ
記憶を辿ってみると、クラフトビールに出逢ったというよりも、そもそもお酒の多様性に触れたのは仕事で飲食事業に携わったことが大きかったと思います。イタリアンレストラン運営に関わる中で、料理人やソムリエが料理やお酒に向き合う熱い気持ちに触れたことも影響しています。不思議なことに、レストランにきたお客様は、提供された料理とお酒を囲み、仲間や恋人、仕事仲間と会話をし、帰り際には満面の笑みでお店を後にするんです。その笑顔を見ると「目の前の悩みなんて大したことないんじゃない?好きな人たちと美味しいものを食べて、お酒飲んで、アッハッハって笑えば、それで万事良いんじゃないか?」と思わせてくれました。
同時に、レストランに滞在する数時間の間に、こんなにも人間を幸せにする料理やお酒に自然と興味が湧いて来ました。そこでイタリアのワインやビールという存在を自分の中で認識し始めました。ワインであればキャンティのこともそこで知りましたし、イタリアビールにモレッティがあると知って、私の中の「食」の世界が少しずつ広がっていくことを感じて、楽しかったのを覚えています。
料理に合うワインをソムリエさんに聞いたりして、初めて、同じワインでも品種、作り手、産地、醸造年によって味わいが違うものなんだと知り、ブワ〜っと世界まで意識が広がって、ワクワクしましたね。ビールもモレッティ以外のビールが産地ごとにあるんですよね。次の土地にはどんなイタリアンビールがあるのか?そんな発見が楽しかったです。
クラフトビールとの出逢い
食の世界が私の中で広がりつつある頃、社会人大学院で経営学を学ぶことにしました。そこは、企業で活躍されている大人たちが集い、平日の仕事終わりや週末に講義を受け、仕事の悩みを経営学的アプローチで解決できないか模索する場でした。
当然、頭を使った後は飲みに行くわけです(笑)そこで、クラフトビールを教えてもらいました。最初に知ったのは、よなよなエールが有名な「ヤッホーブルーイング」さんです!
大学院の仲間に、恵比寿にあるYONA YONA BEER WORKSに連れて行ってもらい、そこで全種類のビールを注文しました。その種類の多さに驚きを隠せなかったですね。
しかも、普段飲み慣れた「ピルスナー」とは違って、全部個性があるんです。こんなに味を変えられるの?どうして色が黄色くないの?私の頭にはハテナが浮かびっぱなし!
実は当時は味の違いについてあまりよくわかっていませんでした。ホワイトエールは飲みやすいなあ、IPAは苦いなあ、くらいしか判別できませんでした。でも、全部美味しかったんですよね。
身近なビールで、こんなに種類があることを知って、更に私の「食」における世界観が広がり、心が豊かになる感覚があったことを今でも覚えています。
社会人になり、「食」の豊かさに触れることから「お酒」のもたらす多様性の楽しさを知り、自分にとってもっとも身近な「ビール」にもたくさんのスタイルがあることを認識したのがきっかけでした。
クラフトビールにハマった背景については、まだ続きがあります・・(笑)また次回以降、その変遷を綴りたいと思います。今日もありがとう!乾杯!
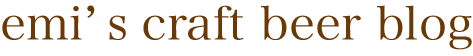

-120x68.png)
コメント