みなさん、こんばんは。えみのクラフトビールブログへいらっしゃいませ。
クラフトビールについて広く語るブログにしていきたいと思っていますが、「クラフトビールってなに?」とか「もちろん知っているし飲んだこともあるけど、詳しくは知らない」という方もいらっしゃると思います。そこで、クラフトビールを知るために、まずは歴史を振り返ってみたいと思います!
クラフトビールの歴史を振り返ってみよう!
クラフトビールは、「地ビール」として始まった
地ビールが誕生したのは、1994年。ビールの製造免許の取得には、年間最低製造数量が2000kl以上必要だったところ、酒税法改正により60kl以上でも取得できるようになったのです。つまり、小規模でもビール醸造が可能になったということです!
それまで大手ビール企業しかビール製造ができませんでしたが、少量でもビールづくりができるということで、ビール製造事業に参入する人たちが現れ始めました。
しかし、新規参入者は醸造経験がある方ばかりではありません。醸造技術のノウハウを習得していくまでには、当然ながら時間がかかりますよね。となると、品質や味わいも安定しないといったことも起きてくるわけです。
また、地ビールは大手ビールと比較すると、単価が高い!そりゃそうです。ビール製造は装置産業と言われ、大規模の設備投資が発生する産業で、作れば作るほど単価が安くなる仕組みです。小規模で利益出すためには、単価を高くしないと事業が成立しません。
ある意味、装置産業は大量生産が前提であるのに対し、【小規模でもできる】という革命が起きたわけですよね。大量生産することで品質が安定するといったこともありますが、小規模だとその品質管理も難しくなります。
地ビールブームは次第に下火に
地ビールブームは1999年頃まで続きますが、次第に、高価格・品質や味わいが安定しないということで客離れを起こし、地ビールブームは下火になっていきました。値段や味わい以外にも、文化的背景も影響していると言われています。
というのも、ピルスナー以外のスタイルも登場したわけですが、日本ではまだ様々なスタイルのビールに馴染みがなかったということです。
つまり、ビール文化がまだ多様性を受容できるフェーズではなかったということです。
ブームが下火になってから、需要が激減し、多くの醸造所は淘汰されてました。一方で、そのような厳しい時代の中で、地道に品質改良に努めたりして、生き残った醸造所もあったのです。
「クラフトビール」として第2次ブームを迎える
2011年頃から地ビールではなく「クラフトビール」としてイメージ刷新して、徐々にクラフトビールと呼ばれるようになっていった背景がありました。その時には、品質改善もされ、国内外のビールコンペティションで日本の小規模醸造所も受賞し始めたりと、知名度を上げていきました。
また、消費者の価値観の移り変わりにもちょうどマッチしていき、「クラフトビール」としてブームが再燃し始めました。
消費者の価値観というのは、嗜好多様化・クラフト志向の高まり、また様々なお酒の中から自分の好きなお酒を選択するという活動の中で自己表現していくといったものです。
この価値観の変容が、多様性のあるクラフトビールとの相性が合った、ということも後押ししたのではないでしょうか。
コロナ禍以降、更に醸造所が増加
第2次ブームの最中、コロナ禍となり、飲食店は大打撃を食らいました。私は正直、コロナ禍で経営を継続させることが難しくなった醸造所もあったのではないかと懸念していました。
コロナ禍を経て、やっと普通に外食できるようになった今日、クラフトビールの醸造所がどのような変化を遂げているかを調べてみたところ、驚くべきことに右肩上がりで増えていることを知りました!!これには衝撃!!今や日本全国で800箇所以上の醸造所があるようです。
それだけ多様性に触れる機会も増えたのではないかと感じます。今後、ニッチなこのクラフトビール市場に興味を持ち、ファンになってくれる人たちがどれだけ出てくるでしょうか。
私はこれからも美味しくて楽しいビールにもっと出逢いたいので、クラフトビール業界を応援します!
さて、ここまで簡単にクラフトビールの歴史について振り返りましたが、「普通のビールと何が違うの?クラフトってどんな意味なの?」という疑問を抱いているあなたへ!
クラフトビールには定義があります。元祖クラフトビールの発祥の地・米国と日本における「クラフトビール」の定義についてご紹介します!
「クラフトビール」の定義は?
米国
ちなみに、米国のクラフトブルワリーの業界団体であるブルワーズ・アソシエーション(Brewers Association)によると、クラフトビールは以下のように定義されています。
Small(小規模であること)
Annual production of 6 million barrels of beer or less (approximately 3 percent of U.S. annual sales). Beer production is attributed to a brewer according to rules of alternating proprietorships.
年間製造量が600万バレル(約72万キロリットル)以下であること
Independent(独立していること)
Less than 25 percent of the craft brewery is owned or controlled (or equivalent economic interest) by a beverage alcohol industry member that is not itself a craft brewer.
クラフトビール事業以外の酒類関連企業による株式保有比率が25%未満であること
Brewer(事業としてビールづくりを行なっていること)
Holds a Brewer’s Notice issued by the Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau, or its successor, or control the intellectual property for one or more brands of beer, have that brand or brands brewed for it in the United States, and have as its primary business purpose the resale of the brand or brands it controls.
酒造免許を持って醸造していること
さすが米国・・・小規模の規模が日本のそれとはまるで違う!株式の保有率についても条件があったりと、かなりビジネス色が強いなあ、と感じます。日本はどうでしょう。
日本
日本では、2018年に全国地ビール醸造者協議会(JBA)において下記3点定義が定められました。※全国地ビール醸造者協議会(JBA)より引用
酒税法改正(1994年4月)以前から造られている大資本の大量生産のビールからは独立したビール造りを行っている。
1回の仕込単位(麦汁の製造量)が20キロリットル以下の小規模な仕込みで行い、ブルワー(醸造者)が目の届く製造を行っている。
伝統的な製法で製造しているか、あるいは地域の特産品などを原料とした個性あふれるビールを製造している。そして地域に根付いている。
少量かつ地域に根付いていることが大事であることが伝わりますね。そう思うと、クラフトビールでも地ビールでも呼び方はブルワーの想いがしっくりくる方で良い気がします。
今日はクラフトビールの歴史と定義について振り返りをしました♪今度は、ビールのスタイルなどに触れて行けたらと思います!
ここまで読んでくれてありがとう!今日も乾杯!!
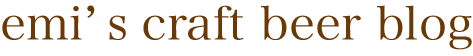
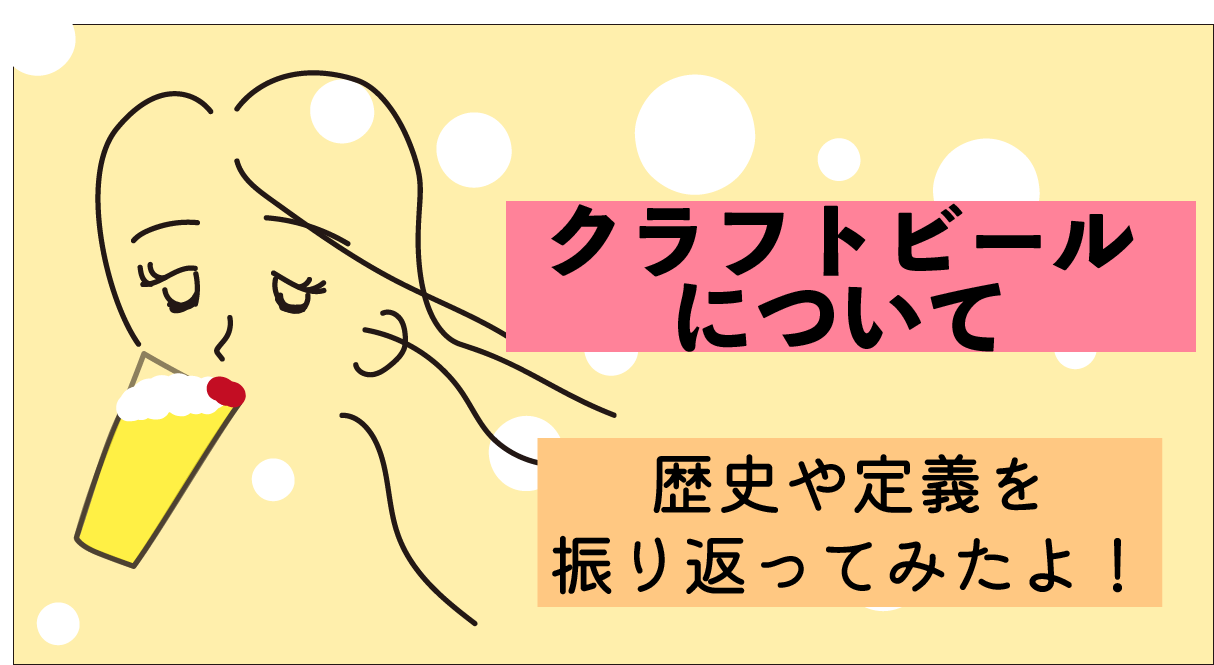
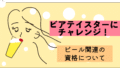
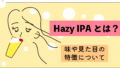
コメント