先日のブログで「ビアテイスター」という資格にチャレンジします!という記事を書きましたが、ちょこっとその背景について綴ってみようと思います。
ビール関連の資格は受験する人の数だけ、理由があると思います。私は受ける人が納得していればそれで良いと思っています!受験を悩んでいる方にとって、参考になれば幸いです。
社会人大学院の論文テーマが「クラフトビール事業」だった
私は社会人大学院を2020年3月に卒業しました。その時の卒業論文テーマが「クラフトビール事業成功の鍵」で、当時1年間かけてクラフトビール事業について研究をしていました。経営学の大学院だったので、クラフトビールの味わいについての研究・・・というよりも、経営学の「事業化」にフォーカスした内容でした。
しかも私が論文を書き始めた頃は、ちょうどクラフトビールを好きになり始めたタイミングと同時期だったため、実はちょっと変わった(?)ことに、味わいやスタイルなどの知識よりも先に、メーカーがいかに事業を成功させるか、といった観点での研究から深堀りが始まったのです。
論文を書き上げるまでは、必死に関連調査を行っていました。調査という名目で、合間合間にビアスタイルや醸造方法についてのセミナーに参加して勉強をしていたものの、「飲みまくって体感する!」みたいな経験を心ゆくまでできなかったんですよね。
卒業と同時にコロナ禍突入
だからこそ、卒業後には「バーやパブに行って飲みまくるぞー!」と息巻いていた途端、コロナ禍突入し、あれよあれよと自粛モードになり、飲食店に行けるような状況ではなくなってしまいました(涙)家飲みで色々なクラフトビールを飲んでみたりしたけれど、やっぱり一人で飲むのはちょっと寂しかったですね。今思い返しても、切ない記憶が蘇ります。
みんなで飲みに行って、色々な種類のビールを注文して、感想を言い合いたかったですね。これが好きだとか、苦いとか、この料理と合うねーとか、もしコロナ禍じゃなかったら、私の経験値は格段に上がっていただろうなあと思います・・・。
しかし現実は厳しいかな。独学(?)で色んなクラフトビールを飲んでみたけど、自粛が続く環境下では、次第にクラフトビールを定期的に飲み続けるといった日常生活からは遠のいていきました。
マイブーム再燃
あれから少し時間が経過した今、ひょんなことからまた「クラフトビール」の世界に再び触れる機会があり、コロナ禍を経た現在に、まさか全国の醸造所数が増加していたことや、クラフトビール業界は変わらず業界全体を盛り上げようとみんなが頑張っていることを知り、胸が熱くなりました。
そして何より、「やっぱり、美味しい!!」を体感。美味しいビールは人を幸せにすることを実感しました。
このビールの多様性の素晴らしさや面白さは大切にしていきたいですし、魅力を発信するためには、しっかり知識は持ち合わせていたい。そこで、資格取得をしてみようというところに至りました。
そう、私は現在進行形でクラフトビールを学び中なんです。
ビアテイスター資格取得までの学習について
勉強方法ですが、テキストが手元に来たら、本格開始したいと思います!(おい、そんなんで大丈夫かっ?!)
それまでは・・・とりあえず毎日飲んで、飲んだビールのスタイルについて調べたりレビューしたりして、知識の向上に努めたいと思いますっ!(正々堂々とクラフトビールを飲めますね♪)
というのは半分冗談で、今も日本ビール検定のテキストを常に持ち歩いて、少しずつ勉強を始めています。官能評価がやはりどんなものか想像できないため、ややびびっています。
勉強の様子もブログに書いていきたいと思いますので、応援のほど、よろしくお願いします!
今日もお疲れ様でした!乾杯!
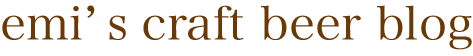
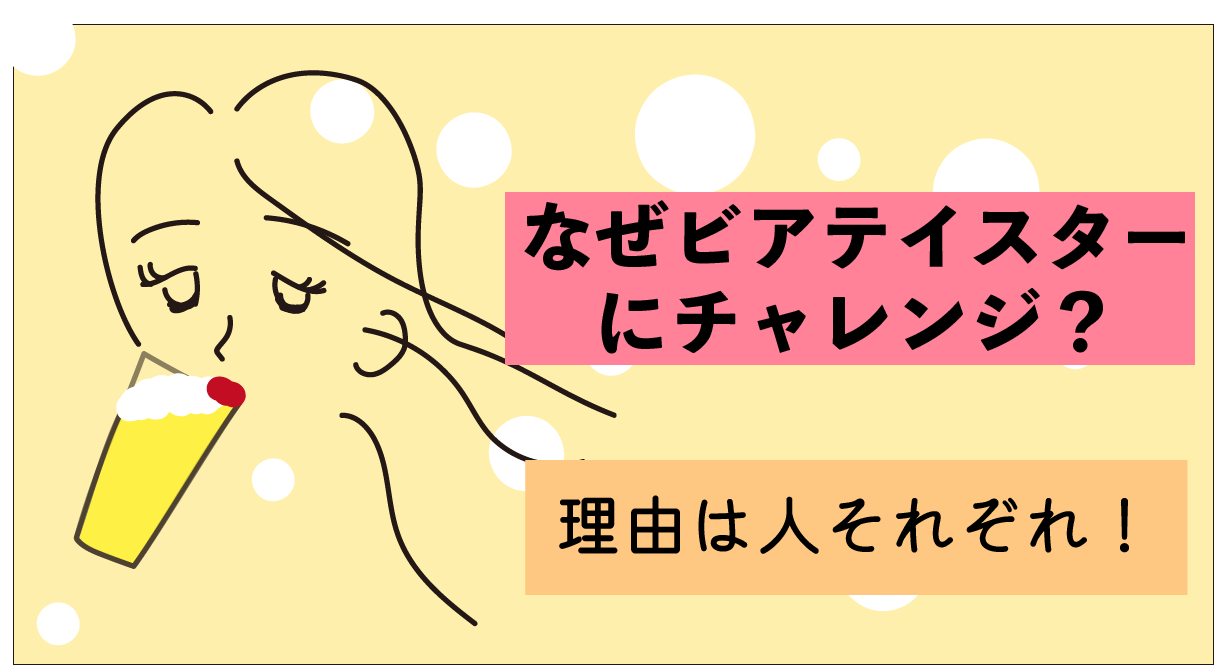
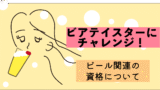
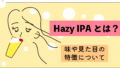
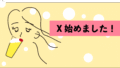
コメント